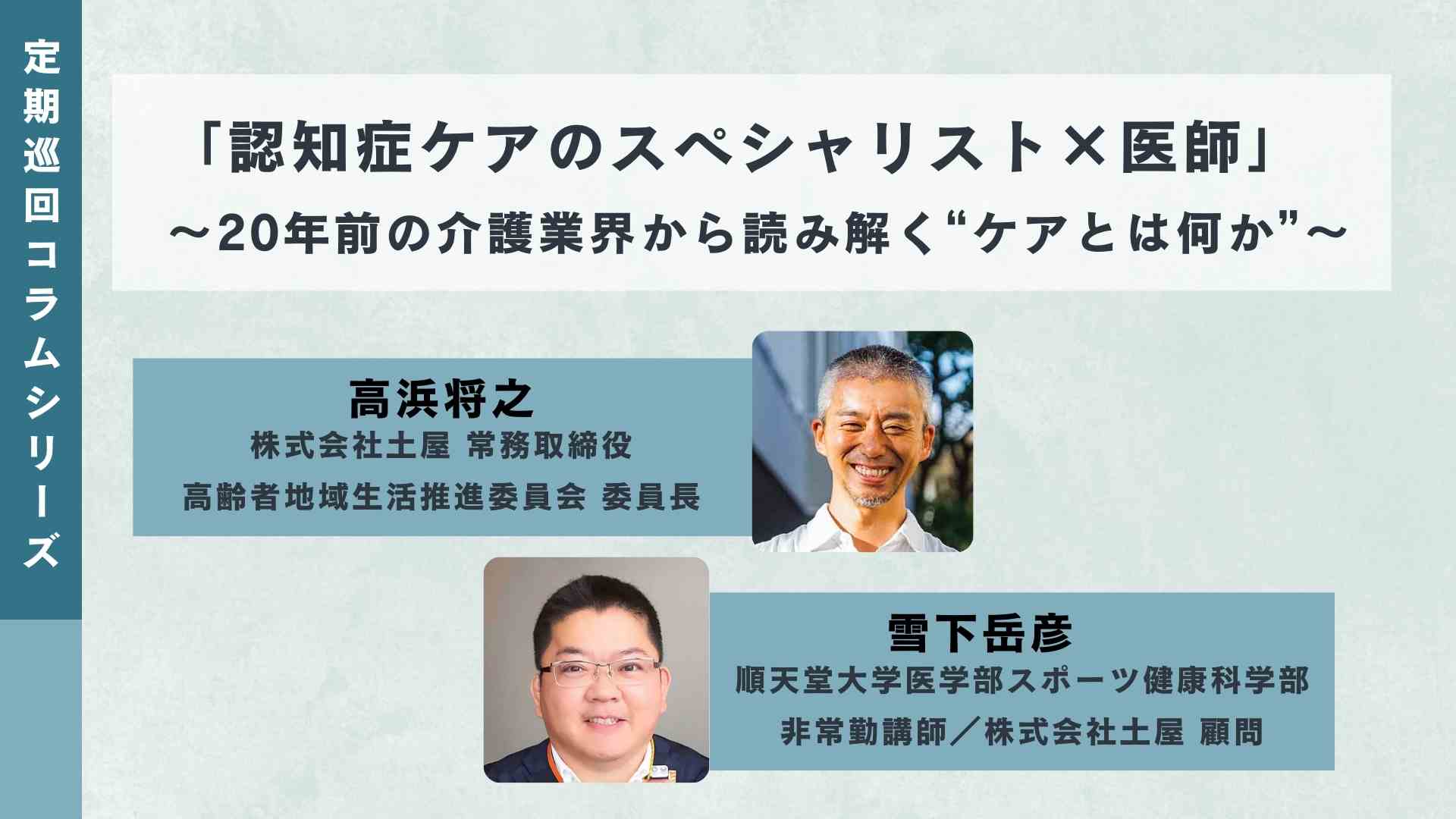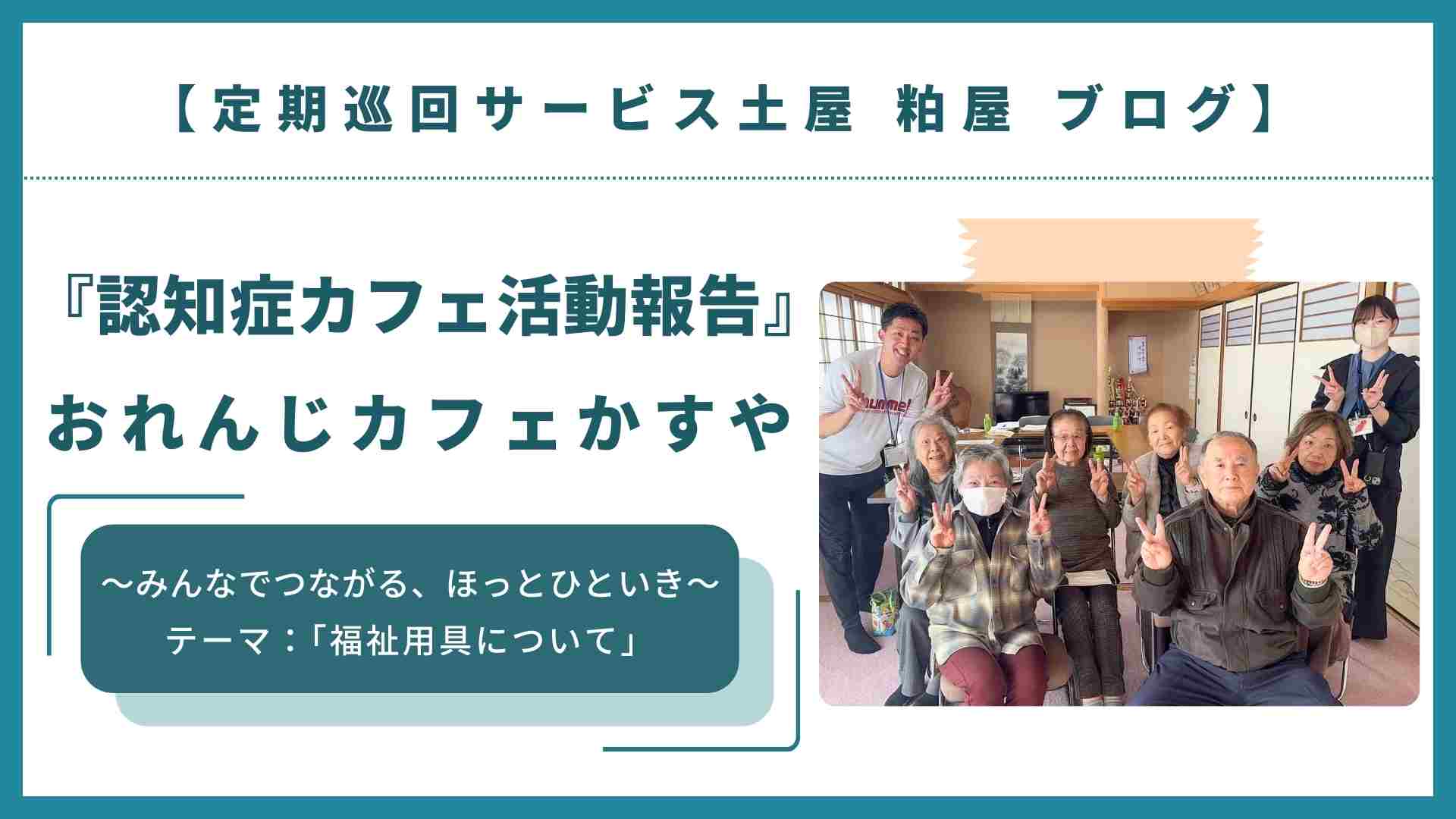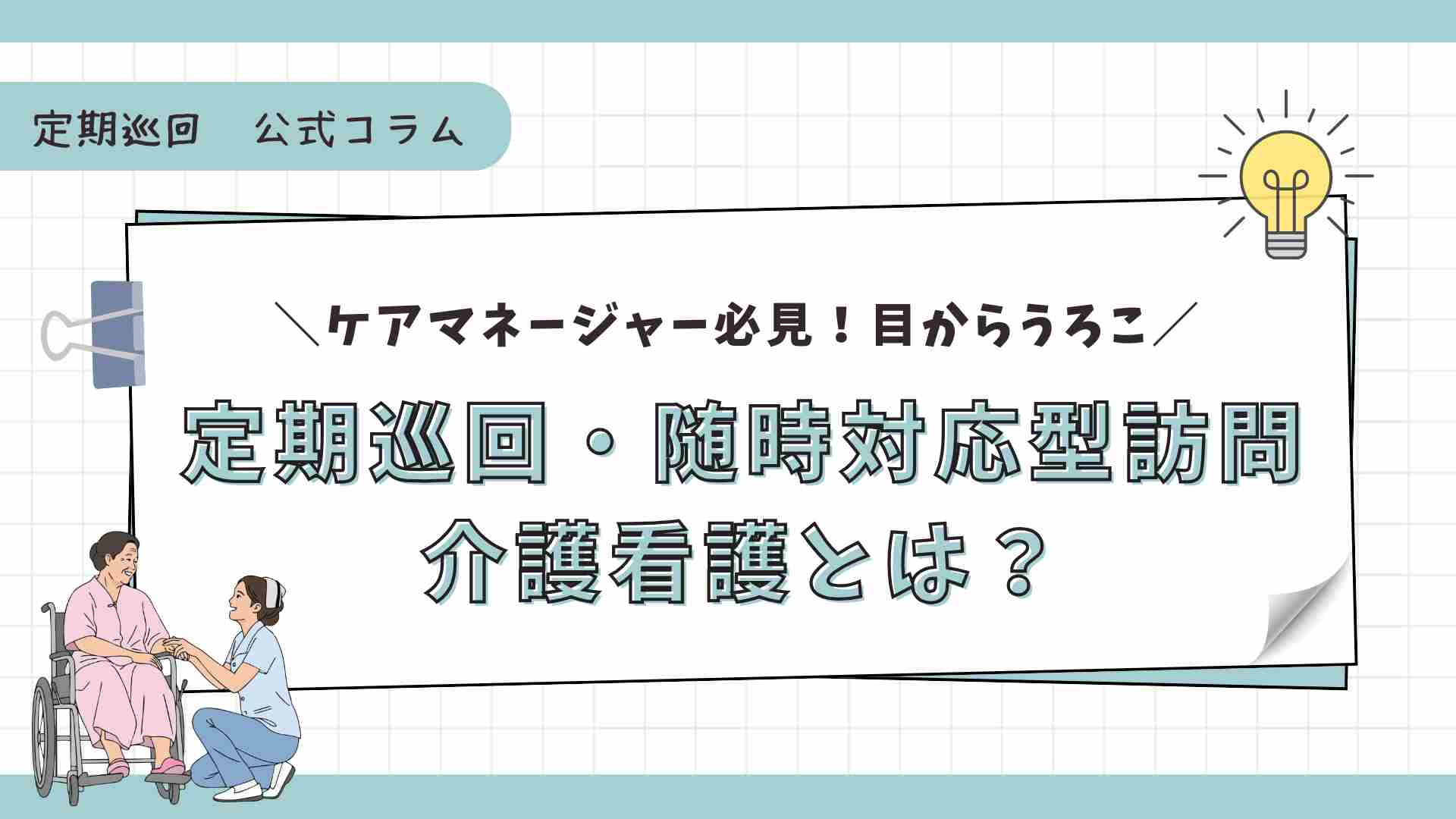不適切にもほどがある~20年前の介護業界から読み解く“ケアとは何か”~
「不適切にもほどがある」(高齢者地域生活推進委員MTG 2024/5/16)を題材とし、介護×医療の視点より、認知症ケアのスペシャリストである高浜将之常務取締役と医師の雪下岳彦氏により、「ケアのあり方」についての対談が行われました。
かつての介護業界で行われていたケア内容を紐解くことで、現在の介護業界に求められている真のニーズに迫るとともに、今なお介護職員が抱えて続けているケアの悩みについても鋭い洞察がなされました。
▸対談者
▸対談テーマ
- 排泄介助の在り方とは
- 身体拘束はなぜいけないのか
- 嘘も方便について
今回は、この3つのテーマについて対談していきたいと思います。
排泄介助の正しいあり方とは
 常務取締役・高浜将之
常務取締役・高浜将之以前の介護業界では、利用者さんよりも、ケアをする側の都合が優先されてきた状況があります。
例えば排泄では、オムツの中にパットを複数枚重ねて、それを一枚ずつ抜いていくというように、ケアワーカー側の負担が少なくなる形が取られていました。
今から20年ほど前の介護業界だと、おそらくほとんどの事業所でこのようなケアが行われていたと思います。
そして大型施設の一部では、今なお、同じようなことが継続していると思われます。
効率化を図る上で、こうしたケアが行われてきたと思いますが、一方で、利用者さんの安眠を妨げたくないという思いも、確かにそこにあったと感じます。
やはり、50~60人のオムツ交換をする中で、利用者さんが定期的に目を覚ますことに対して申し訳なく思う気持ちがあり、素早いケアを重視したと思われます。
とはいえ、衛生面的には清拭がしっかり行われていないわけで、“睡眠を妨げても、しっかりとケアをするか”、あるいは“ケアを素早くして睡眠を保つか”、
このはざまに立ってケアワーカーは今も仕事に従事していると思われます。
もっとも、さすがに便であれば、以前の介護業界でも清拭しないなどは有り得ないわけですが、問題は尿です。
目に見えず、夜間の睡眠を優先したいという気持ちもあり、パットを抜くだけにしてしまうことは多々あると思っています。
雪下先生、医療の観点からは、尿汚染がもたらす皮膚への影響はどのようなものですか?



尿がある程度残っていて、そういったケアをすると、皮膚ダメージになりやすいですし、高齢者自体が、ちょっとしたことで皮膚の傷ができやすいので、
できれば清潔な状態を保つのが理想とは思います。



陰部洗浄であれば、ケアワーカー側も、おそらくきれいになっていると思えますが、横になった状態で清拭するだけだと、
どれくらいきれいになっているかが感覚値でしかありません。
ケアワーカーの中には、過去に「陰部洗浄を毎回すると逆に肌を痛める」と教わった者もいるようです。
もちろん尿が肌についたままのほうが肌を痛めるというのが通念だと思いますが、ここはいかがでしょうか?



石鹸などを使って頻回に洗うことは、肌のバリア機能を失う一因にはなるので、それは一つ理解できるところです。
ただ、お湯だけでどれくらい洗えているかの評価は非常に難しいと思います。
肌の状態が健全であれば、ある程度、水で流しておけば、肌自体に問題が起こる可能性はかなり低くなると思うので、そこらへんじゃないかなと思います。
ただ、マンパワー的なところでの妥協点で、パットを重ねたり抜くなどの状況になってしまっているのかと思いますが、
人というより排泄の部分にしか目がいかなくなってしまうのが問題だとは思います。



確かに、大型施設の配置基準や人数などで、物理的にできない部分もあることが、ケアの効率化に至るバックグラウンドとしてあると思います。
多くの事業所では、夜間は清拭がメインで、朝にしっかり陰部洗浄するというのがスタンダードだと思いますが、
尿汚染の度ごとに陰部洗浄すると、睡眠は妨げられます。
睡眠が減るのもストレスになるわけで、清拭/陰部洗浄と睡眠のバランスについては、どう考えたらいいんでしょうか?
これはケアワーカーがずっと悩んでいるところだと思います。



これはかなり難しいところですね。
それぞれ睡眠のパターンがありますし、一度起きると寝られないタイプの人もいるので、そういうことも考えながらするしかないかなと思っています。
夜でも起きてきれいにしてもらってから寝るのがいい方もいるだろうし、途中で起こされるのが嫌な方もいるだろうし、難しいところだと思います。



やはり、その人のことをどれだけ知っているかが重要だということですね。
一度目が覚めてなかなか寝付けない人に対して、夜間帯のケアを充実させすぎても、それはそれでバイオリズムがおかしくなってしまうこともあるだろうし、
皮膚の強さ・弱さもそれぞれ違うので、夜間は清拭だけで朝起きてしっかり洗ったほうがいい方もいらっしゃるんだろうなと。
以前の介護業界では、パットを複数枚重ねて抜く他にも、尿量が非常に多い人に対しては、
パットを2、3枚重ねた上で、そこに穴を開けて、一回分の吸収量を上げるといった細かい技もよく使われていましたが、
それ自体も、もともとは安眠を妨げないためにスタートしたと思うんです。
けれど、それは表層的なことでしかなくて、結局ゴワゴワしていたら安眠を妨げることにつながるので、やはりそれぞれの睡眠パターン、皮膚の状況を踏まえて、
お一人お一人に合わせたケアをしていかなければいけないと改めて思いました。



オムツをせずに上手くコントロールできる状態をなるべく保つことが理想とは思うんですが、あくまでそれは理想ですね。
ただ、生活リズムが壊れてしまうと、排便排尿リズムも壊れてしまいます。
日中や一日全体の過ごし方が、排泄の背景にある可能性はあるので、その辺は全体を見ていくことが必要なんじゃないかと思います。



確かに、夜間の排尿・排便がどういうタイミングで、いつどんな形で出るのかは、日常の生活がかなり影響する部分だと思うので、
ピンポイントでその部分だけを切り取らないということですよね。
そこだけ見てしまうと、その人の生活自体を見失ってしまうことになるのかなと。
排泄では他にも、オムツを反対向きにつけるなども、20年ほど前はよく行われていました。
これはテープが前にあると剥がれてしまうので、後ろ向きに穿いてもらって漏便を防ぐというものですが、完全に身体拘束です。
そういったことやオムツを重ねて穿くなどの場合、精神面での影響はいかがでしょうか?



それはやはり快適とは言えない状態だと思うんです。
自分の尿意をもってトイレまで行けるかどうかなど、その方の認識状態によっても大きく変わるとは思いますが、
蒸れたオムツを何枚も付けること自体、動きやすくはならない。
そういったところでのシンプルなストレスもありますし、認知状態の悪い方でも、
それが精神的なストレスになって、感情的なところや行動に現れてしまうことは十分あると思います。
ケアする側の方が、それを一度経験してみるのもいいかもしれないですね。
利用者さんの立場になって、尿を吸いこんだ状態のオムツが肌に当たる感覚などを経験して、みなさんにお伝えするのもいいのかもしれないとは思います。



一度体感するだけでも、ケアのあり方に気付きをもたらすということですね。
身体拘束はなぜいけないのか



次に身体拘束について伺いたいと思いますが、「認知症の人の歴史を学びませんか」(宮崎和加子 著/写真:田邊順一/中央法規)という本があります。
その本には、昔はいかに認知症の人たちが劣悪な環境で生活していたのかが、いわゆる老人病院の写真をふんだんに使って描かれています。
廊下でパンツを脱がされて、そのまま支援が行われていたり、牢屋のようなところに入れられている人がいたり、
野戦病院のように、ほとんど動く隙間もない所に一様に寝かされていたり。
4点柵(患者がベッドから降りることを防ぐため、ベッドの周りを完全に柵で囲むもの)は当たり前で、70年代後半には、
いわゆる「つなぎ」が開発され、両手が紐で縛り付けられていたこともありました。
こういう身体拘束が当たり前のように行われていた時代がありますが、
近年、身体拘束を禁止する法律ができたこともあり、それ以降はもちろん行われなくはなりました。
けれど介護職の中には、身体拘束は「法律で禁じられているから駄目」という認識の人たちが一定数います。
「じゃあ、どうしようもない時には、どうしたらいいんだ」という思いがやっぱりあるわけです。
実際に、M&Aで土屋グループにグループインした会社の中には、以前から身体拘束を行っており、発覚したということがありました。
(*土屋グループでは、身体拘束発覚後、所轄行政に報告を行い、必要な処分を受けています)
別のやり方もあるかもしれないですが、安易にそこにたどり着いてしまう人たちもまだまだいて、
そういった意味では、身体拘束がそれを受ける側の人に対して及ぼす心理的・身体的ダメージ、もしくは尊厳の問題について、改めて解説をお願いします。



身体拘束に関しては、まず基本的には、その人の自由を奪うことになるのですべきでない、その権利を奪うべきではないということが根底にあります。
それに加えて、身体拘束によって起こる、特に身体的なダメージとして、筋力や運動機能の低下で、転倒しやすくなるなどがあります。
基本的に拘束が強い状態というのは身体全般にリスクがあって、
身体をなかなか動かせない状態になったり、内臓や呼吸も衰えてくるというように、状態をさらに悪化させることにもつながります。
拘束の箇所によっては皮膚にダメージが起こることもあります。
精神的にも「拘束されている」というのが多大なストレスになって、それがさらに精神状態を不安定にしてしまいます。
身体拘束は、一時のその状態を抑えるという意味では、やむを得ない部分があるとは思うんですが、
そのデメリットはより長期に続く可能性もあるので、その辺の見極めは非常に大事だと思います。



ありがとうございます。
私は以前、有限会社のがわ(現 株式会社土屋の子会社)という会社の代表取締役を務めていましたが、
当時、あるグループホームから“のがわ”に転居されてきた入居者さんがいらっしゃったんです。
その方は、グループホームの2階のベランダから飛び降りて、両足を骨折して入院したんですが、事業所側はもう受け入れられないと。
家族としても、その事業所には戻さないということで、最終的に“のがわ”に来られたんですね。
飛び降りた原因として考えられるのが、その事業所は入り口がオートロックで施錠されていて、常に外に出られない状況になっていた。
でも、その方は出たくて仕方がなくて、でも出口がないのでベランダから飛び降りた、こういうことだと思うんです。
というのも、安全に出られる場所があれば、人はそこから出て行こうとするものです。
“のがわ”では当時、基本的には入り口の施錠をしなかったんですが、
それは「施錠して、その箱から出られなくすること自体が身体拘束だ」という感覚で運営していたからです。
そういった意味では、自由が制限されるストレスというのは、極限までいくと、2階から飛び降りるところまで行きつくのかなと。
雪下先生は、出口の施錠などが、大きな意味での身体拘束に当たると思われますか?



身体拘束というのは、基本的には身体の一部を何かにつなぎとめるといったことで使われることが多いですけど、
施錠に関しては拘束という点では変わりないですよね。
精神的な拘束に近い状態だと思います。
いわゆる問題行動には、少なからずその人にとっての理由があることが多くて、周りからは理解できなかったとしても、
自由を奪われるなり、自分にとってストレスや不快となることを避けようとすることで、そうした行動が起こりがちになります。
認知機能が落ちてくると、より単純反応的に、ストレスを回避する行動を取ることが起こり得るので、一口に問題行動で片付けてしまうよりは、
その背景にどういうことがあるかを俯瞰で見ることが大事になってくると思います。



ありがとうございます。
先生のお話を聞いていて思い出したんですが、昔は特養などの施設には回廊型という、行き止まりにならない廊下があるところも多くあって、
その頃は「利用者さんがずっと歩いていられるから、どこにも行かなくなるし、いいものだ」と言われていました。
でも、回廊型の何が良くないかというと、
介護職員たちが「その人がどうして歩いているのか」「どこに行こうとしているのか」について全く興味を持たなくなってしまい、
ちゃんと確認することなく、「歩いているからいいや」で終わってしまう。
要は、入居者の行動の背景を考えなくなることが大きな問題だと言われており、それが「回廊型は悪だ」とされる所以です。
入居者の方が外に行ったり、怒ったりするなどの理由や背景を、ケアワーカー側がどれだけ知るかというところが、
今の認知症ケアの基本的な考え方になっていると思うんです。
研修で私たちはよく、「真のニーズはなんなのか」という言い方をしますが、例えば利用者さんが「家に帰りたい」と言っていても、
その人が本当に家に帰りたいかどうかは実は別問題で、自分の居場所がないからそう言っているのかもしれないし、居心地が悪いから、あるいは、
どうしても気になることや不安になっていることがあるからそう言っているのかもしれない。
家に帰れば帰ったで、「ここは家じゃない」と言われたりもするわけですが、それは時間の逆進性が起きているからであって、
例えば96歳のおばあちゃんが自分は16歳だと思っていたりするわけです。
そもそも本人が生きている時代が違うんですが、本人がどういう状態にあって、
何を理由に、今何をしたいのかをちゃんと聞いて、背景を理解するのが必要だと感じます。
自由を奪うということについても、改めて思うことがあるんですが、誰が何の権利でその人の自由を奪うのかなと。
これも、人として扱わなくなってしまった結果かもしれないと感じます。
例えば国の法律では、人が人を殺すことを禁じていますが、死刑制度は国が人を殺すわけです。
ただ、そこには誰かを介するわけで、何らかの形で人が人を殺害するのを認めていることになる。
論理上、死刑囚が人ではないという定義をしない限りは矛盾でしかない。
尊厳という問題の中で、どこかに縛り付けられることが許されるとか、どこかの箱から出ちゃいけないといったことも、
刑務所に入れられた犯罪者と同じような位置づけじゃない限り認められないことで、そう考えると、身体拘束の根本的な問題は、
拘束する側がされる側の利用者さんを「人じゃない」と、どこかで思わないと、この行動には踏み切れないと思うんですが、
先生はいかが思われますか?



心理学の実験で「囚人の実験」というのがあって、スタンフォード大学の学生さんを刑務所の看守と囚人の二役に分けてそれぞれで行動させると、
同じ学生内で、いわゆるロールプレイをしているにもかかわらず、主従関係ができてしまうことが示されました。
看守役が囚人役にかなりひどいことをしても心が痛まないという心理状況になっていくという有名な実験ですが、
介護現場で以前起こっていたことはそういう状態に近いのかなと思います。
基本的にはケアをする側と受ける側がどうしても主従関係になりやすく、その延長線上に身体拘束もあるのではないかと思います。
ただ、基本的には主従の関係ではないんですよね、介護する側とされる側というのは。
だから、介護業界の「利用者第一主義」という言葉も分からなくはないんですが、それも危険な要素をはらんでいて、
そうすると利用者が第一で、介護者が第二という主従関係の位置づけにもなりかねない。
医療でも、昔は「お医者様」という時代があって、その後、「患者様」という時代になって、患者の権利が強くなってしまった時期があります。
前者は『白い巨塔』の時代ですが、患者様の時代になって立場が逆転しました。
このような「どちらかが上に立つ」といういびつな関係性が、様々な医療の問題を引き起こしてきました。
やはり、医者と患者、介護する側とされる側で理想なのは、対等な関係であったり、共同作業というところですよね。
だから利用者中心というか、精神科の領域では「クライエントセンタード」という言い方をするんですが、利用者を中心においてというところですね。
上下という考え方よりは、あくまで対等という観点を、特にこれから介護に関わる人に持ってもらうのが大事なんじゃないかなと思っています。



ありがとうございます。
認知症ケアの日本での基本的な考え方も、イギリスの臨床心理学者トム・キットウッドが提唱した
「パーソンセンタードケア」がベースになっているところでは、確かに利用者第一主義という上下の関係と、
利用者を中心にどう支えるのかという考え方が、一見、似ているようで、大きな違いがあると感じました。
私が“のがわ”で認知症ケアにずっと関わっていた中で大切にしていたのが、支援する側とされる側を固定しないということでした。
要は、スタッフが何でもかんでも支援してあげていると、初めは「ありがとう」と言っていた利用者さんが、気づいたら「すいません」と言っている。
初めて人に親切にされると嬉しいですけど、ずっとやってもらっていると、「ありがとう」がだんだん「すいません」に変わって来てしまう。
今先生が仰っていたことですが、世話をされすぎると、あるいは支援する側とされる側の関係が固定されると、明らかに上下関係、主従関係ができてしまう。
基本的に僕らは「利用者さんが快適に幸せに過ごせるようになること」を目指していた中で、それは違うと。
どちらかというと、「利用者さんに僕らが『ありがとう』を言う支援をしよう」という話をずっとしていたんですね。
言葉は悪いけど、利用者さんをめちゃくちゃ“こき使う”わけです。「あれやってくれ、これやってくれ」って。
しまいには世話好きの利用者さんたちの横で、「アー疲れた」って言うと、
「あんた疲れてるんだったら肩揉んであげるから」って、僕の肩をよく揉んでくれていました。
要は、利用者さんが内発的、自発的に行動してくれる。
そうすると身体も頭も使うし、感謝の言葉を僕らから伝えられることで精神的にも豊かになっていく。
やはりケアワーカーが“お世話をする仕事”になってしまうと、関係が固定されて主従関係になってしまう傾向があるので、
お世話をするのではなく、あくまでその人たちをどう豊かにするか、どうすれば幸せに、より元気になってもらえるのか、
より自発的に生活してもらえるのかを根拠をもって目指すのがケアワーカーの仕事だと、改めて感じました。



利用者さんが肩を揉んでくれたりというのは、ある意味、理想的というか、それが日本中にあればより望ましいんじゃないかという考え方だと感じますが、
利用者なり、利用者の家族は、“やってもらうことが当たり前”になりがちなので、そのマインドがなかなか難しいところもあるのかなと思います。



確かに僕らもその根拠をご家族にしっかり説明していかないと誤解を受けかねないところもあるので、コミュニケーションと根拠・理由を、どうご家族さんと共有するかも大切ですね。
嘘も方便?



介護業界では、ケアワーカーが利用者さんに苦し紛れに嘘をついてごまかそうとする状況がしばしば見られます。
これは昔から今に至るまでずっと続いていて、認知症ケアのパイオニアの人たちも、
初めの頃は「嘘でもその人が納得して幸せになればいいんだ」と言っていたんですよね。
私もそう教わった時期もありましたが、そこに関してはずっと違和感があったんです。
パーソンセンタードケアでも「嘘をつくのは絶対に良くない」とされていますが、先生はこれについて、いかが思われますか?



日常生活において「嘘も方便」という場面はないことはないと思うんですが、基本的には社会においても嘘をつくのは良いこととされないですし、
介護の現場も日常や社会の延長にあるわけなので、基本的に嘘がベースになるのは良くないと思います。
信頼関係の問題ですよね。
介護、医療も、結局はある種の共同作業であって、それをするに当たって信頼関係は根底にある、一番大事なところになると思うんですが、
嘘はその信頼関係を築く上で問題になります。
そして、一度崩れた信頼関係を取り戻すのは、それを築くことに比べるとはるかに難しい。
介護の現場に関わらず、世の中一般でもなかなか難しいので、推奨される行為ではないと思います。



ありがとうございます。
例えば、入居者さんが施設に入られた当初は、当然ながら皆さん「家に帰る」と仰いますが、昔はごまかしていたんです。
「もう遅くなっちゃったから」とか、「夕方になったら送るから」とか。夕方になったら「暗くなったから明日にしよう」というように。
けれど、ある時から“のがわ”ではごまかすのを止めることにしました。
やはり、利用者さんにそういう適切じゃない嘘をついて支援するのは良くないからと。
これも身体拘束の話につながることに、今初めて気づきましたが、当たり前のように嘘をついていい相手というのは、
そもそもその人を、ちゃんとした人として見ていないからそうなるんだと思います。
ごまかすのを止めるとどうなるかなんですが、“のがわ”で以前、中国に仕事で行くことになった息子さんが、
一人暮らしの母親を心配して入居の手続きを取ったケースがありました。
入居者となった母親は、入居後に「帰る。息子はどうしたんだ。私を見捨てたのか」と何度も言われるわけです。
けれど、「息子さんがいつか迎えに来るから」とか適当なことを言わずに、ずーっと付き合い続けたんですよね。
「息子さんは頑張って中国で働いていて、大事なお母さんが一人暮らしでいるのを心配して、ここを準備したんだ。
だから息子さんもここにいることは分かってる、大丈夫だ」と。
もっとも、ご本人が納得しても、2分後には「息子はどうしてるんだ」と尋ねるわけで、このやりとりを毎日何時間も続けるんですが、
ケアワーカー側としては嘘をついている時よりも負い目がなくりますし、
それを実践していたら、ある時から入居して3~4か月後に「家に帰る」と言う人はいなくなったんですよね。
外に出たいという理由はあっても、家に帰るという理由はなくなった。
「ここが私の家でしょ」というようになっていき、そこが自分たちとしては成果や自信につながったと思います。
こういう方向性で、これからも土屋は全国で認知症の人の支援体制を築けたらと思っておりますが、
今の考え方や方向性についてご意見をいただけますでしょうか。



非常に素晴らしいと思います。
お伺いしていて、意外とそれも大事なのかなと思ったのが、介護する側の嘘をつくことに対する罪悪感のところですね。
その場しのぎで適当にペラペラと嘘を言える人もいるかもしれないですが、
騙すことに対して引け目を感じてしまう素直な方もいらっしゃると思うので、嘘をつかないというやり方は、
介護する側の心理的なモヤモヤを晴らしてくれて、そういった状態で仕事に臨めるというのは、
実は介護する側に大きな影響を与えているのかなと思いました。
最後に
▸常務取締役 高浜将之
今日は排泄・身体拘束・嘘も方便という、三つのテーマに分けて対談しましたが、すべて共通したものだということを感じました。
一言で言うと、尊厳というものをどれだけ重く捉えているか、ということだと思うんです。
高齢者であっても認知症であっても、「一人の人としてどう尊重するか」というのは、
言葉で言うだけなら簡単だと思いますし、「人として見る」というのは当たり前だとも思いますが、意外とそう思えていないから超えてしまう一線がある。
どこかで軽んじてしまうからこそ、パッド交換も適当になってしまうし、身体拘束にもつながるし、嘘もつくしというように、不適切なケアの根底にあるものは、そこだと思うんですね。
これは、「人って、なんなんだろう」というのを、実を言うと僕らがあんまり考えないで日々の支援をしているからじゃないかなと。
尊厳というものの認識やディスカッションが、介護業界自体に足りていないと感じます。
「人を人として当たり前に見る」ということが、僕らが思っているよりはるかに難しいということを、先生と対談する中で改めて感じました。
ありがとうございました。